❶ MENU ❷
❼ 空腹豚児 (すばらとんこ) のレコード放浪記 ❺
Ą INTRODUCTION
˘ 私がクラッシックにめざめた頃
Ł オーケストラにおけるコントラバス
Ľ フルトヴェングラーのこと
Ś レコードにおけるトチリ (ミス)
Š 私の好きな音楽
Ş 技巧をひけらかす音楽
Ť レコードファンの心得〜「ケチ」であれ!!
Ź ボスコフスキーの思い出
Ž わが楽しみ〜東京レコード店めぐり
(どうぞ、お好きな項をクリックしてください)
❼ 空腹豚児のレコード放浪記 ❺
Ą INTRODUCTION 
私はよく、名フィルの団員からこう聞かれる
「ねえ、あなた今何枚レコード持っているの?」
とたんに、私は返事に窮してしまう。 なぜならばそれに答えることが、まるで自分の
恥をさらけ出してしまうような気がするからである。
正確に数えてみた事はないが、どう少なく見てもレコードとCDを合わせると、ゆうに
二万五千枚は越えているだろう。 (1998年6月現在)
暇つぷしに作ったカタログを見てみたら「運命」が165種類、「第九」が121種類あった。 (
ああ、恥をさらしてしまった ! )
どうしてこんなに集まってしまったのか・・・・。 やはりこれが人のいう趣味・・・?
そう ! 私はレコードが好きで好きで仕方がないのである。
でもよく考えてみると、趣味がレコードというのはどうも具合が悪い。 というのは、
音楽に関するもの、つまり自分が商売としているものが趣味というのは、何かにつけて
具合が悪いものではなかろうか。
名フィルの団員諸氏でも誰だって、音楽教室で一日二回「新世界」をやって、家へ帰ってからまた「新世界」のレコードを聴いて「ああ、やっぱりドヴオルザークはいいなあ!!」なんて思う人はいないだろう。 私も名フィルの中で、将棋や釣りなんかに一生懸命になっている人を見ると、つくづくうらやましく思う。 自分も昔楽とは全然関係のない趣味を、とことん楽しんでみたい。 でも、例えぱ将棋は駒の動かし方位は知っているが、
頭が疲れるし、何よりも負けるとトッテモくやしい。
それに釣りはなんとなく残酷で、おさかなさんが可愛そうな気がする。
やっぱり私にはレコードしかないのだろうか。
( 1983年
)
˘ 私がクラッシックにめざめた頃 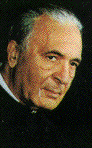
ブルーノ・ワルター
(1876〜1962)
私が初めてクラシックのレコードを買ったのは高校二年の時、そう、今から約二十年
ほども前になる。(あ、おじん ! )
忘れもしない、プルーノ・ワルター指揮、コロンビア交響楽団の「英雄」である。
どうしてこのレコードを買ったのか? 別段クラシックが特に好きな訳でもなかった。しかし、その頃の小生の友人達にはクライ連中が多く、その何人かはクラッシックの
ファンだった。 そして毎日「運命」がどうの「田園」がどうのと話題にしていたのだ。
私は彼等より一段上をいっているのだ、ということを無言のうちに示したかったので、ぺ−トーヴェンの中でもちよっとシブイ「英雄」のレコードを最初に買ったわけだ。
当時の二千円は、高校生のフトコロには大変痛かった。
虚栄心と引きかえの、ワルターの「英雄」・・・・ 。
そのレコードを、小生は毎日毎日飽きもせす、ビクターのポータブルプレーヤー(千八百円の!)
で繰り返し聴いた。 でも、どうも面自くない。 それにやはりポータブルでは、シンフォニーを聴くにはちょっとお粗末すぎるのではないか
? と漠然と感じていた頃、友人が当時八万円もするステレオを買った。 小生は真っ先に、「英椎」とその他
舟本一夫なんかのレコードを持って、彼の家へ向かったのである。
その友人はステレオと一緒にベートーヴェンの「第七」のレコードを新しく買っていた。 小生はまたしても先を越されたくやしさを味わった。
表題のないシンフォニーのレコードなんか買いやがって ! と。
それはクリユイタンス指描ペルリンフィルによる演奏だった。 第一楽章はやけにリズミカルだ。 そして第二楽章・・・・。 なんと荘重で悲しい音楽なのだろう・・・
とりわけ、バスのオクタープでブーブーいっている音が体にこたえて、感動のあまりじんましんが出た。
あの楽器を弾いてみたい! そうだ、大学に入ったらオーケストラをやろう !
・・・
今思えばそれが人生の間違いの始まりだっだ。
今「第七」を弾いていても、でてくるのは冷や汗ばかりで、決して「じんましん」は
出てこない、
( 1983年
)
Ł オーケストラにおけるコントラバス 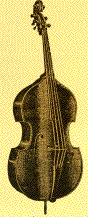
今から十年も前だろうか、ある音楽教室でのお話。 楽器紹介でヴィオラ、チェロと
続き、いよいよ次は我がコントラバス。 その時、司会者が得意そうにこう解説した。
「さて皆さん、コントラバスはオーケストラの中でサイテイの音を出します。」
我々バス一同ガクッときた。 そしていたくプライドを傷つけられたことは言うまでもない。
また、こんな話もある。 朝比奈大先生が初めて名フィルに客演された時の事。
先生はヴァイオリンに向かってこう言われた。
「皆さん、ヴァイオリンはオーケストラの顔なんだから、もっど堂々と弾きなさい!」
するとこれを聞いたバスの連中が、
「じゃ俺達は何だ?オーケストラの尻か?」
「いや一もっと恥すかしい所かも知れないギ」とポゾボソ・・・・。
このようなつらい体験の毎日を送っているせいかどうか、コントラバス弾きというのは
妙にいじけたところがある。 バス弾ききに限らずオーケストラ奏者だって、自らを卑下して「所セン、我々ガクタイは・・・」などど言う事が多いようだ。
ある評輪家がオーケストラを建築にたとえて、作曲家は設計技師、指揮者は現場監督、
そしてオーケストラはその現場で働く土方である、と言った。
これはけだし名言であると思う。 いかに住み心地のいい家をつくるか、という最終の
任務は、常に士方の腕に任されており、ちよっと家の建てつけが悪かったりすると、まず土方に文句がくる。 土方には決してその完成した家の住み心地を味わうことはできない。
そこで我が愛するレコードであるが、確かに音の缶詰めであり、ナマの感動に遠く及ばぬ、という人々ば多い。 しかし、そこには間違いなく既に完成された家としての音楽がある。
私の場合ナマを聴くと、音楽よりどうしても現実に目に入ってくるプレイヤーの奏法の方に気をとられてしまい、音楽そのものを楽しむことができない。
しかしレコードにはそれがない。 これが私が趣味として、いまだにレコードを愛せるゆえんではないかと思う。
( 1983年
)
Ľ フルトヴェングラーのこと 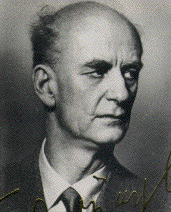
ウィルヘルム・フルトヴェングラー
(1886〜1954)
最近のレコード界でのフルトヴエングラー人気はすごい。 没後四十五年にもなろうというのに、次から次へと発掘される未発表録音の数々。 そのどれもが売れ続けているというのだから、一体この人気の原因はどこにあるのだろうか。 名フイルにも、フルトヴエングラーと美空ひばりの大ファンという、まことに理解に苦しむ人が以前いた。
彼のフルヴェンへの造詣の探さには遠く及ぱないが、私のフルヴェン体験を今回は書いてみたいと思う。
私が高校の時、友人に「ペト七」を聴かされて人生を誤った話はすでに書いた。
その後、私はどうしても「ペト七」のレコードが欲しくなり、その頃は、どの指揮者のものが良いとかいうことが全然わからなかったので、ジヤケットの黒のタートルネックが
いかにもカッコよかった、カラヤン大先生のものを買ってきたのである。
第一楽章はやたらにテンポが速く、落ち着かない。 こんな筈じやないな・・・と思っていると、続く第二楽章、有名なテーマ「タータタ、ターター」を、カラヤン先生はすごくテヌートさせていて、リズムがぼけてしまっている。
私の抱きかけていた「ベト七」のイメーシを見事につぶされ、ガッカリしていたところに、またしても友人が先を越して、フルトヴエングラーの「ペト七」のレコードを買ってきたのだ。 音はモノラルでいかにも古めかしかったか、カラヤンと全然違う。 荘重で、高枚生の耳にも何かひとつひとつの音に、気迫のようなものがこもっているような気がした。 あの第二楽章も、リズムをはっきり重々しく刻んで、いかにもそれらしい。
続いて聴いたブラームスの第四番のレコード、これで私はすっかりフルトヴェングラーに参ってしまった。 冒頭のテーマ「テイーラ」を、フルヴエンは「ティーーーラ」とやるのである。 同じテヌートでも、このテヌートには命がこもっていた。
最近NHKで放映されたフルヴェンの特別番組で、そのブラームスの四番をやっていた。私はうっかり見過ごしていたが、あとでフルヴェン+美空ひばりファン氏からお借りしたビデオを見て、青春の日々の感動がよみがえってくるような気がした。
それは実に十年以上ぷりの、プラームスを聴いての感動だった。
( 1983年 )
Ś レコードにおけるトチリ (ミス)
私のレコード歴が二十年を超えることは恥ずかしながら白状したが、その間いろいろ興味深い珍盤
( ? ) にも巡り会うことができた。
レコードを買ってきて家で針を降ろす。 その繰り返しのなかで今までいちばんびっくりしたのは、オットー・ゲルデス指揮、ベルリン・フィルのブラームス「第四」のレコードを聴いたときだ。 第一楽章のクライマックスで、なんとホルンが一小節早く、あの有名なテーマ(冒頭と同じ)を堂々と吹いているのである。 私は一瞬我が耳を疑った。
あらためてスコアを見ると、そんな筈は絶対にない。 あきらかにホルン奏者がトチッていたのである。 でもきっとスケジュールの都合かなんかで、とり直しができなかったのだろう。 このレコードはつい最近まで廉価盤としてカダログに残っていたが、四年前にめでたく廃盤となった。 さすがにドイツ・グラモフオン社も恥ずかしくなったのではあるまいか。 このように、絶対であるべきレコードにも、時々ひどいミスがそのまま記録されていることがある。 バーンスタイン指揮、ニユーヨークフイルのバルトーク「オケコン」のレコードの中でも、トロンボーンが楽譜にないところで盛大に飛び出しているし、カテイン(P〉、ディヴィス指揮ロンドン新響による、ラフマニノフのピアノ協奏曲第二番のレコードでは、第一楽章の中間部の一番の聴かせどころのクライマックスで、トランペットが見事にヒックリ返っている。
スタジオ録昔でもこんな有様だから、時々FM等で放送されるライプなどは、もっとすさまじいミスが一杯広のだ。 あの天下のペルリンフィルでさえも、信じられないようなアンサンブルの乱れはわりと日常茶飯事だ。(それにしても先日小沢征爾が指揮した、ペルリンフィル百年記念フェスティバルの、チゴイネルワイゼンのアダマはひどかった!) しかし私は思うのです。 全くミヌのない、血のかよわない演奏より、たとえミスがあっても白熱しきった演奏のほうが、どんなにか人の心に訴えるだろうか・・・と。
(ただしこれは、プレーヤーとしての私個人の弁朝では決してありません)
( 1983年
)
Š 私の好きな音楽 
エドゥアルト・グリーク
(1843〜1907)
私は基本的にめめしい音楽が好きである。
めめしいというと誤解があるかもしれないが、要するに旋律の美しい叙情的な曲を愛好しているのである。 この要素が満たされていれば、たとえ我がクラシックでなかろうとも、例えぱR.クレイダーマンや、さだまさし、ユーミンのたぐいであろうとも感動をおぼえる。 クラッシックの作曲家の中でめめしい作曲家といえぱ、やはり後期ロマン派あたりに集中するようだ。 チャイコフスキー、プッチーニ、グリークあたりが、小生の今のところお気に入りの作曲家たちである。
しかし、この中でだれか一人をといわれたら、私は迷うことなく、グリークの名をあげだい。 例えぱ、チヤイコフスキーなど、めめしさの点では他に並ぶもののない程の(?)巨匠だが、(一部には、そのように演奏する演奏家が多すぎるのか? 彼ば不当に誤解されているのであり、本当は構築性をもった大作曲家なのだという声も多いようだ〕たとえば「悲愴」の最終楽章など、悲しみのあまり泣き叫び、のたうちまわり、ドラの一発の後トロンポーンのコラールがでてくるあたりでは、「もう、いらん
! 」という感じにさせられる。
そこへいくどグリークはいい。 彼の音楽はあくまで内省的であたたかく、何かこう、人問の心の暖かさ、すばらしさ、といったようなものを必ず感じさせてくれる。
私は常日頃、自分の葬式には必ず「ソルヴエーグの軟」のレコードをかけてくれるよう、妻に頼んである。
そこで空腹豚児推薦のグリークの必聴盤を一枚 !
グリーグ弦楽作品集/ノルウエー室内○ (スウエーデンBIS = LP 147 )
本当に心の暖まる、すぱらしい一枚です。 ぜひ皆様、一度聴いてみてください。
( 1983年 )
Ş 技巧をひけらかす(!?)音楽
世の中にはいろいろな音楽家がいるが、クラシックの中には演奏家が「私はこんなに技巧があるんですよ、こんなに指がまわるんですよ!」という事を、さもひけらかす為にあるような曲というものが存在する。 例えぱ、タランテラとか無窮動とかいったたぐいはこうした分野に入るだろう。 前者の場合6/8拍子のイタリア舞曲だが、〈毒グモに刺されて苦しみにのたうちまわる様〉というのがこの舞曲の元祖だという。 断未魔にのたうちまわる様を技巧をひけらかす為に使うとは、西欧人というのは何とも残酷な人種だ。 しかし何といっても、こうした音楽の中で一番ポビユラーなのは、R・コルサコフの
「くまん蜂の飛行」ではないだろうか。 もともとはオーケストラ曲であるが、さまざまな楽器によって、いろいろな演奏家が独奏曲にアレンジしてチャレンジしている。
私がレコードで知る眼りでも、フルート、ファゴット、オーボエ、バイオリン、チエロ、トランヘットから、何とコントラパスに至るまで、実ににさまざまである。
中には、ホフナング音楽祭のレコードで、テユーバ吹きがこの曲にチヤレンジして、あまりのバカバカしさに、吹きながら自ら笑ってしまう、という珍盤もある。
題名の「くまん蜂」というイメージを求めるならぱ、チェロかファゴットあたりが一番
近いのではないか。 ヴァイオリンだと蚊みたいだし、コントラバスに至っては、まるでモスラかラドンが飛び回っているみたいた。(
年がバレますね !? )
( 1983年
)
Ť レコードファンの心得〜「ケチ」であれ!!
名古屋人はよくケチだと言われる。 そう言われてみると、小生も思い当たるところがあって、ドキリとさせられる。 何をかくそう私のレコード遍歴も、ケチケチの歴史といってもいい位だからだ。 レコードファンになって間もない頃、好きなジヤンルといえば室内楽とかソロではなく、なんといっても大コーラスつきの大オーケストラ曲であった。理由はカンタン、演奏家が大勢の方が同じレコート1枚買うにしても、何かトクしたような気がしたからだ。 バーンスタインの指揮したマーラーの「千人の交響曲」のレコードが出た時など、私は泣いて喜んだのである。
またレコードの収録時間も、30cmで片面25分以上入っていないと、何かソンしたような気分になったものである。 「悲愴」「英雄」が1枚にカップリングされレコードが出た時は、演奏者が超三流であったにもかかわらず、まっ先に買った。
このような小生のシ向を、多くのレコードファンの友人たちはバカにした。
そして、規模の大きいシンフォニーばかり聴いていた小生に向って、
「お前、たまにはカルテットも聴いてみろよ。ペートーヴエンの後期のなんか、しびれるぞ!」と言ったのである。
ケチのくせにみえっぱりの名古屋人・・・、知らないジャンルのことを得意そうに言われたことにカチンときた小生は、その足ですぐ、ペートーヴェンの十四番のカルテットのレコードを買うぺく、レコード店に向かった。
店にはバリリとブダペストのものが置いてあった。 ここで私は迷わず二千円のブダペストではなく、千円のバリリを購入した。 そして、家へ帰って針をおろしてみたのだが、なにせ安物のプレーヤーのこと、フォルテのところで針が飛びそうになり、“バリ、バリリ・・・”と大きな音がした。
「なるほど、これかバリリの真髄か!」とは決して思わなかったけれど、けっこう心にしみた。 そしてバリリのぺ−トーヴェンは、小生の青春晴代の忘れ難い思い出となったのである。 大学時代、このレコードを夜中(12時すぎ)
に下宿で一人で聴いて、何度死にそうな気分になったことか。 あの頃は純枠にアマチユア・・・ディレッタントであったんですなあ。
( 1984年
)
Ź ボスコフスキーの思い出

ウィリー・ボスコフスキー氏と筆者が彼にいただいたサイン
W‐ポスコフスキー……。オールド・ファンにはなんと懐かしい名前だろう。
小生もクラシックに興味を持ちはじめてからすぐにこの名前を、レコ芸のロンドン・レコードの広告欄で知って以来、あの、ちょっと丸顔でいかにも人のよさそうな写真に好感を持ち、とくに毎年発売されていた、ウィーン・フィルのニユー・イヤー・コンサートのレコード等で、ずいぷんウィンナ・ワルツの醍醐味を味わわせてもらって来た。
またTVなどで自らヴァイオリンを本当に楽しそうに奏きながら指揮をする姿を見たりして、とかく堅苦しいクラシック音楽の世界で、本当に音楽することの楽しみを教えつづけてくれた(ドイツ語でspielenというのかな?)、小生にとっては、とても大切な人だった。
この一月、そのポスコフスキーおじさんがわが名フィルヘ、ウィンナ・ワルツを振りに来たのだ! 今まで雲の上の人のように思っていた小生にとって、このコンサートは本当に楽しみなものだった。(正直いってプロのオケで、このような気持になるのは本当に珍しいし、また貫重なことだと思うが・・・)
それまでの名フィルのニユー・イヤー・コンサートは、なんとあの中日ドラゴンズの選手やアイドル歌手なんかを招いて、彼らのカラオケがわりにされたり、アトラクションにつきあわされたりした、まことに安易な内容で、正直、楽員はみんなうんざりしていたのだ。
さて、ボスコフスキー氏を招いてのコンサートの練習の初日、氏は奥様を同伴されて、我が練習場へ姿を現わした。 堂々たる長身、端正な横顔。 あゝ・・・しかし、時は老いの影を、残酷なまでに彼に投げかけていた。 彼が姿を現わすまで、我々は、ひよっとしてヴァイオリンを奏きながら指揮してくれるかも・・・と淡い期待を持っていたのだが、到底これは望むべくもないことだと悟らざるを得なかった。 かなり足腰が弱っておられる様子で、練習は終始イスに座って行なわれたのだが、なかなか自分の思うような響きが出てこないいらだちからか、気持ちが高まってくると思わず、立ちあがって手を大きく振りあげた。 「モーツァルト、ぺ一トーヴエン、ブラームスー・・・どんな音楽にもそれぞれの難しさがあります。 ウィンナ・ワルツにも、それを演奏するうえでのいろいろな難しさがあります。 私はこの練習で、皆さんに少しでもこの音楽の心を感じとっていただきたい」
我々のオーケストラの音は、限られた2日間だけの練習で、彼の思っているようなものに到達するとはとても鬼えなかった。 我々もいらだったし、彼のいらだちも気の毒なほど小生に伝わってきた。 しかし小生は、彼の指揮する姿のすべてが、ウィーンの雰囲気、ウィンナ・ワルツの楽しさを伝えるすべになっている気がして驚嘆した。
「音をもっとそろえて」とか、「そこはもっとピアニッシモで」とか、まことに恥ずかしい注意ぱかりであったが、すべてそれが単にアンサンブルのみのためでなく、その音楽に欠かせない場所での注意だったのにもびっくりした。
休憩の時、小生は色紙を持って氏のサインを求めに行った。
大そうにこやかにサインをするその右手は小きざみにふるえ、たどたどしく、ああ、マエストロどうかいつまでもお元気で・・・・との感慨を禁じえなかった。
一緒に持参したウィンナ・ワルツ大全集のレコードの解説書を、とても嬉しそうに見てくれ、rこれは75年のニューイヤーコンサートのときのものだ」とか、ウィーンフイルの写真の中の何人かのメンバーの名前を語ったリした。
いよいよコンサートの日。 最初はいく分手さぐり状態だったオーケストラも、ポスコフスキー氏の練習のととはうってかわった幸福そうな指揮ぷりと、奥様のアデアによるさまざまな演出(ポルカ「狩」や「郵使配達」など)と、それに、ウィンナ・ワルツを心から楽しもとする心あたたかい聴衆の皆さんのおかげで大そうもりあがり、最後の曲「美しく青きドナウ」のヴァイオリンのトレモロが出てきた時には、なにか自分がウィーン・フィルの一員として、ムジーク・フェラインザールで演奏しているような錯覚におそわれて、思わす目頭が熟くってしまった。 アンコールで演秦されたrラデッキー行進曲」に合わせて手拍子を打つお客緑のリズム感も、ムジーク・フエラインに勝るとも劣らなかった、と思う。
こうして演奏会は大そう良い雰囲気のうちに終わり、マエストロはその素晴しい笑顔を残して、我々のオーケストラを去った。
今、小生の部屋の壁にはポスコフスキー氏のサインと、あの人なつっこい丸顔の写真が飾られている。 その写真に向かって、小生は心からこう言いたい。
「ボスコフスキー先生、本当にありがとうございました。
どうか、いつまでもお元気で・・」
( 1985 年1
月 )
Ž わが楽しみ〜東京レコード店めぐり
小生は愛知県在住である。
名古屋から名鉄に乗ってゴトゴトと南へ35分、知多半島の真ん中あたりに居を構えている。 レコード・コレクターとしてこの地理的条件は小々不利な事が多い。 要するに
“ドイナカ”のために、なかなか小生の欲しいようなレコードが手に入らないのだ。
「運命」「夫完成」の同曲異演盤やマーラー、ブルックナーのシンフォニーなどを聴きかじっている頃はまだ良かった。 それがひょんなことから「ぺ一ル・ギユント」をきっかけとして北欧音楽に狂い(このいきさつは、また書いてみたいと思っている)、シペリウス、ニ一ルセンを経て、いまやアッテルペリィ、アルヴエーン、ステンハンマーなどの秘曲を捜し回る身である。
このように欲しいレコードがどんどん特殊化、変態化してきたため、いきおい名古屋では小生の欲しいレコードにお目にかかる機会が少なくなってきてしまった。
よく考えてみると、小生が大都会だと思っていた名古屋も、全国的に見たら“偉大なる田舎”なのだそうだから、これはやむをえないところなのかも知れない。
そのため“そうだ、東京へ行けば、きっともっといろいろ小生の求めているようなレコードにお目にかかれるかもしれない。 よ一し俺ら東京さいぐだ1”ということになった。 クラシツクファンになってから初めて、東京のレコード店めぐりをした時の感動を、小生は忘れられない。 いつもレコ芸誌上で広告を通してしか知らなかった数々の店へ実際に足を運んだ事のよろこびは、各々の店についてそれぞれ一文が書けるほどの数多くの印象が残っている。 現在では、年に最低二回は東京でレコード店めぐりをしないと、なにか時代の流れにとり残されてしまったような気になるから恐ろしい。
最近では「東京レコード店MAP」などという大そう使利な本も出ているので、ひとたび上京のチヤンスがめぐってくると、もう有頂天で、その一週間ほど前から、レコード店めぐりの最も良いコースを、ああでもないこうでもないと考えるのである。
この時の小筆は本当に幸福だ。
こうしたレコード店めぐりを通じて、いつの間にか、東京の地理にも詳しくなったし、
又、店によって実に様々な個性があるものだなあ、といろいろ感ずる面自さもある。
店のタイプを分けると、大体大きく二つに別れるのではないだろうか。
まず店がメジヤーで、とにかく薄利多売の店。
店内は明るく在庫も多いが、こうした店ではそんなに特殊な、「あった一1」というようなレコードにはめったにお目にかかれない。 しかし、安さにつられて、“すぐには聴かないが、なんとなく持っていたいレコード”を大量に買って、サイフをハタクのもこうしたタイプの店である。
その逆に、店主のシュ味がこうじて店を始めたような、マイナーなタイプの店。
このようなタイプの店には、名古屋ではまずお目にかかれない。
店はあくまで狭くうす暗く、時にはマンションの一室だったりする。
もちろんクラッシック、それも輸入盤や中古盤の専門店で、入っていくと、ジロッと“何しに来た”というような目で見られる。
時にはそこの常違みたいなムサイおっさんと店主が話しこんだりしていて、こちらは全くおかまいなし、といったことも多い。
「二一ノ・ヴァランの新しいアリア集が、フランス盤で出ましてね一」
「シユポアの7番のコンチェルトはお持ちですか」
勝手に二人でモソモソしやべっている。
ふん、てやんでえ、とこちらは居心地の悪さにさいなまれつつ、エサ箱を接すのだが、
輸入初期モノラル盤などが、それこそ、目の玉のとび出る位高い値がついて入っていて、うんざりさせられるのだ。
こんな、現在再発されているレコードをわざわざ、高い金を出してポロのジヤケットを眺めながら聴くのは、一体どんな人なのかなあーなどと考えながら、しかし、rうわー、あったーっ」と叫んでしまいそうなレコードにお目にかかれるのもこういった店なのが、少々シャクだね・・・。
最近は東京でも、とくに郊外の方に雨後のタケノコのように中古のレコード店が新しく出来てきたようで、小生の興味もつきないが、反面、代々木のジユビターのようにひっそりとその幕を閉じる店もある。 閉店間際の、レコードがほとんど出はらってしまつた店内に、ぼつんと残ったご主人と奥様の姿がほんとうにさみしそうだった・・・。
CD主流になっていくと思われるこれからのレコード界、はたして小生のレコード店めぐりもこの先、一体どんなふうに展開していくのだろうか。
( 1987 年
8月 )
 最初のページへもどる
最初のページへもどる


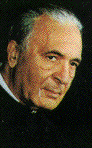
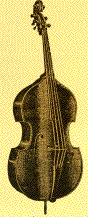
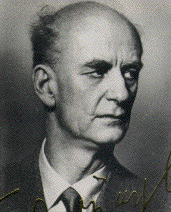


 最初のページへもどる
最初のページへもどる