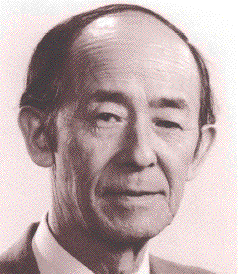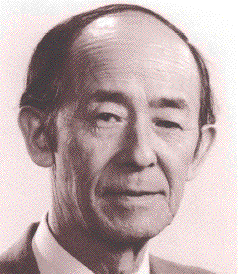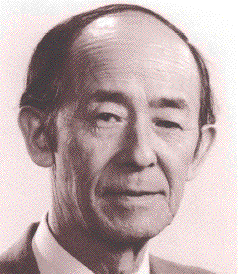
 安部幸明
「シンフォニエッタ」 雑感
安部幸明
「シンフォニエッタ」 雑感
安部幸明 の「シンフォニエッタ」は、彼の2曲の交響曲
= 第1番 (1957) 、第2番 (1960) に続く、「第3番」とも言うべき、演奏時間30分を要する大作。日本フィルの委嘱に応じ1964年に書かれ、翌年1月14日、渡邊暁雄の指揮により初演されている。
作曲者はこの作品について「交響曲と名付けても良いのだが、肩の凝らぬ軽いものなので「シンフォニエッタ」(小交響曲)
としたのだ」と述べている。
しかし他の2曲が3楽章なのに対し、4楽章の堂々たる古典〜ロマン派系譜の大シンフォニーであり、内容的にも「肩の凝らぬ」ものとはとても思えない、充実した内容を持っている。
第1楽章は安部が敬愛したベートーヴェン「エロイカ」と同じ「アレグロ・コン・ブリオ」3/4拍子のソナタ形式。安部の好きなD音を基音としている。第2楽章「モデラート」4/4拍子の3部形式。 第3楽章「アンダンテ〜プレスト」4/4拍子のスケルツォ。 第4楽章「アレグロ・アッサイ」2/4拍子のソナタ形式。 楽器編成は以下の通り。
(Picc. 2 Fl. 2Ob. Col-Ing. 2Cla.(in A, B♭) 2Fg. 4Hr. 2Tp. (inB♭)
3Tb. Tuba
Timp, Tri-Ing. Pt. G.C. T-M Xylop. W-B Guiro Hp. Celesta Strings )
スコアは1973年に日本作曲家協議会から出版されたものが唯一のようだ。幸いにも私は数年前、あるアマチュア・オーケストラで「シンフォニエッタ」の譜面のコピーを取らせていただいたものを持っていた。このたび必要に迫られ、スコアを見ながら改めてCDを聴いてみた。(ヤブロンスキー/ロシアpo. NAXOS)
たいそうな力作である。管弦楽の手法に優れ鳴りも良く、パート間のバランスにも細やかな配慮が凝らされている。
さっと全曲を聴いた感じでは、新古典派というよりはオネゲル、ルーセルなどエネルギッシュ系のフランス近代の作曲家の作風を連想した。
第3楽章のスケルツォなど、オネゲルの「パシフィック231」(1923) を彷佛とさせる「機関車音楽」で、その推進力はまことに素晴らしい。
ただ聴いているうちに、この曲を初めて聴くという人が演奏会の客席で、万一曲に感情移入が出来なかった場合、終るまでの時間がさぞ辛いだろうな、などと思ったりしてしまった。曲の構成はまことにしっかりしており、オーケストレーションも素晴らしいのだが、特に印象に残る主題
(旋律) があるわけでもなく、テンポの変化に乏しく、静かな部分でも直接こころに訴えかけてくるような盛り上がりやハーモニーがある訳でもない。聴き手に対する「サービス精神」が少々不足しているのでは・・・と感じざるを得なかったのだ。
1965年の初演を聴いた音楽評論家・大木正興が、東京新聞に批評文を書いている。
大木はまず「明快な音の使い方、ととのった形式、あざやかな管弦楽法など、熟達した技巧でひきしまった軽い味を出しており、個性のはっきり浮きぼりにされた佳作である」と、曲に対する評価を書き連ねている。しかし続いて「欲を言えば、緩徐楽章をもう少し内容的に強いものにし、また他の三つの速い楽章ひとつひとつには、さらにはっきり色分けされた性格がほしい
(後略)」と記しており、私は強く共感した。
例えば安部の和声学の師・プリングスハイムが学んだマーラーは、その交響曲において全体の構成を実に巧妙に設計し、最初ソロ楽器によりpppで現れた主題が楽器を増やしハーモニーを加え、対旋律を絡ませ徐々に盛り上がり、遂にはフルオーケストラで堂々たるクライマックスに至る手法に卓抜していた。しかし、そこには露悪的と言えるまでの「内的心情の暴露」がベースにあった。
安部幸明は「音楽とは、まず自然にのびやかに響かねばならない」と考える作曲家だった。
音楽の中に自分の内的心情・・・特に苦しみや悲しみといった個人的なものや、政治的な要素を加えるべきではない、と思っていた。
これは安部一流のダンディズムであり、「音楽とは、何より聴いていて楽しいもの」という彼なりの信念なのだろう。
そうしたこともあってか、安部は「実は、緩徐楽章を作るのをいちばん苦手としている。苦手というか、好まないといった方がよいかも知れない」と自著で白状している。彼の言葉を借りれば、「しんねりむっつりなことは、私の分野ではないということだ」という訳である。
「シンフォニエッタ」においては、苦手だという緩徐楽章では、戦後間もなく宮内庁洋楽指揮者をつとめた体験を活かし雅楽調の響きで書かれ、安部の作品では珍しく「日本」を感じさせられる。その主題はストラヴィンスキー「火の鳥」の子守唄をいっそう素朴にした感じで、中間部のヴァイオリンによるカデンツァからは、安部が子供のときに憧れたこの楽器への思いが強く伺える。
「西洋音楽古典派のソナタ形式の70%は速度が速く、また舞曲的なものだ。私はそうした音楽を得意とする」という安部の言葉を読んだあとに、この「シンフォニエッタ」を聞き直してみると、この作品、ひょっとしたら物凄い傑作なのかも・・・という気がして来る。まこと、音楽というのは不思議なものだ。その曲を聴く時の周りの状況
(コンサートホールの実演か、又は自分の部屋又はドライブに行った旅先でのCD、i-pod
か・・・また体調万全の時か、それとも持病の発作で苦しんでいる時か 等々)で、感想は全く違う。一回だけの印象で、作曲家が多大な労力を費やしたであろう藝術作品に「バカの壁」を作ってしまったら、それは聴き手自身にも不幸な事だ。
私はこの「シンフォニエッタ」をこれからも、また聴く機会を持ちたいと思った。
なお先の大木の批評とは別に、「音楽藝術」に掲載された批評に安部は激怒した。「この曲は 死の予告」と書かれたのだ。
「いろいろ批評するのは勝手だが、死という人の一生を安直にと、不快になった」
そこで2か月後の同誌に、安部は批評に対する反論を掲載したところ、大きな反響があったという。いつの世にも曲の本筋と全く無縁な、偏狭な知識と思い込みだけで知ったかぶり風に書かれた批評はあるものだが・・・それにしても「シンフォニエッタ」のどこが「死の予告」なのだろう?
その後「シンフォニエッタ」はレニングラード、ワシントンDCでも演奏され、好評を博した。もちろん「死の予告」とは言われなかった。
残念な事に、この「シンフォニエッタ」が安部幸明の最後の管弦楽作品となってしまった。
作曲家によると「30数段に及ぶフルスコアを書く時、目の疲労を覚えるようになったから」だそうだ。時に安部幸明まだ54才、いかにも早すぎる。
思えば戦後数年間、日本で管弦楽曲の作曲はほとんど行われなかった。オーケストラはほぼ壊滅状態、プレイヤーが徐々に復員して来るなか、「運命」「未完成」などを中心とした「名曲コンサート」なる演奏会が次々に行われ、お寒い演奏内容とは裏腹に音楽に飢えた人々が詰め掛け、会場はいつも長蛇の列が出来たという。(このあたりの世相は、黒澤明監督の映画「素晴らしき日曜日」を見ると良く分かる)
世の中が落ち着いて来た1950年代後半、東京交響楽団、続いて日本フィルハーモニー交響楽団が日本の作曲家によるシリーズを立ち上げ、それが安部幸明の創作の円熟期と重なり、管弦楽の代表作3曲
(2曲の交響曲 & シンフォニエッタ) が生み出されたわけだ。私たちにとって、何と幸運な事だったろう。
ちなみに「シンフォニエッタ」が書かれた日フィルシリーズは1958年にスタート、当初は間宮芳生、入野義郎、三善晃、柴田南雄、武満徹、別宮貞雄、黛敏郎と続いたが、「前衛的で難解」という声が強くなり、調性音楽を手掛ける作曲家の起用に路線が変更され、その結果山本直純、清瀬保二、高田三郎が起用され、安部幸明がつづいたという訳だ。なお高田三郎がこのシリーズで発表した「無声慟哭」は高田令夫人・留奈子さんによれば高田三郎の最高傑作だということで、2010年11月12日に東京芸術劇場で久々の再演がなされた。(内藤 彰/東京ニューシティ管弦楽団)
2012年6月14日、安部の生地広島で「シンフォニエッタ」は久々に再演の時を迎えた。(J-
Classic Libraries (故日本人作曲家のオーケストラ作品簿 山下一史/広島交響楽団) マエストロ・山下の誠実なタクトのもと、広島交響楽団は凄まじいまでの熱演を繰り広げてくれた。
私が密かに心配していたこの作品の「難解さ」は、全くの「危惧」であったことを、鳴りやまない拍手が教えてくれたのである。
雲上の作曲家も、きっと喜んでくれたことだろう。
(一部敬称略) (2012.6.16 /岡崎隆)
(次の資料を参考にさせていただきました。)
「現代日本の作曲家5/安部幸明」 (音楽の世界社 発行/小宮多美江・著)
「日本の作曲20世紀」(音楽の友社=刊/小宮多美江・著)
CD「日本作曲家選輯」安部幸明 (NAXOS 8.557987J) 解説 (片山杜秀・著)
安部幸明/「シンフォニエッタ」フルスコア (日本作曲家協議会・刊 1973)