〜 思い出すままに 〜
佐藤 正知

鬼頭恭一(以下 K と記す)が私にとって身近な存在となったのは、彼が愛知一中を卒業して受験浪人となり、東京大森区(現・大田区)田園調布の私の家の2階に下宿するようになった1940年(昭和15年)からである。当時私は小学校6年生で、家には両親と祖母、
K より2歳年上の姉、私のすぐ上の中学1年の兄・正昭がいた。 K とは同年で以前から交流のあった長兄・正宏は陸軍士官学校の生徒で家にはいなかった。2年後の1942年2月、ビルマで戦死したとき、
K からレクイエムを献呈されることになる。
最初 K が上京したのは、早稲田の商学部受験が目的の予備校に通うためだと私も聞かされていた。ところが、それはどうやら上京のための
K の作戦で、本当の目的は上野の音楽学校 (現・東京藝術大学音楽学部)
であることがまもなく分かった。そこで当然、家業を継ぐことを期待して早稲田受験を許した父親の怒りを買うことになったのだが、それがどのようにして収まったのか、子供だった私にはあまり関心もなかったし覚えも無い。ただ父親の妹であった私の母、つまり
K にとっての叔母が、 K の側に立って兄をなだめたことは確かである。こうして
K は晴れて音楽の道に進むことができるようになった。そしてたまたま私の家のすぐ近くに住んでおられた細川緑先生に作曲を、また東急東横線の現・学芸大学付近におられた水谷達夫先生にピアノを習いつつ猛勉強をはじめた。とくに水谷先生は
K の10歳位年上とまだお若く、名古屋出身ということもあってか、 K
とは気も合っていたようである。
K は私たち兄弟にとって兄貴分のような存在だった。彼は、愛知一中時代に、生徒にビンタを食らわせた教師に抗議して謝罪に追い込んだ武勇伝や、化学教室から硝石や硫黄を持ち出し(盗み出し?)て黒色火薬をつくり、鉛筆のキヤップでつくった弾丸を紙筒の大砲にこめ、向かいの塀をめがけて発射した話を得意そうに聞かせてくれたりした。(
私たちは早速そのまねをした。ただし薬品は薬屋から入手したが。)またあるときには、兄と私は階段をこっそり上がって2階にいる
K を襲撃し、 K が出てくると階下に逃れて、階段の上下で輪ゴムの鉄砲を射ち合ったりして遊んだ。2対1でも結構手ごわい相手だった。
K は“恭ちゃん”のほか“恭坊”と呼ばれることもあったので、私たちはそれをもじって“凶暴”だと云って負けたくやしさをまぎらわせたものだった。
彼はある日、山田耕筰の作曲によるオペラ『夜明け』を見に出かけた。ちなみにウィキペディアによると、『黒船』とも名付けられたこのオペラが、「皇紀2600年を迎えるにあたって奉祝楽曲として初演され」たのは1940年11月25日とのことである。そういえば、もう掘りコタツの入った夜のことだったような気がする。帰宅した
K は、私たち兄弟と姉の前で、「こうやって腹を切りながら歌ったんだよ」と仕草をまじえて声を張り上げ、私たちを面白がらせた。ただし山田耕筰については、明子の記憶によると、彼はピアノの水谷先生と意気投合して、「あんな国策作曲家はだめだ」と気炎を上げていたそうである。彼の理想としたオペラは、ビゼーのカルメンのように、一人の人間の人生ドラマを描いたものであったという。
オペラといえば、「僕はきみたち兄弟をテーマにして、歌劇“アキちゃんとトモちゃん”を書くつもりだ」と、真面目とも冗談ともつかぬ調子で云ったのも多分その頃である。
私どもの家は大森区と世田谷区の区境近くにあった。その区境は簡易舗装された狭い道路だったが、いまでは環状8号線が走っている。
音楽学校に進学した K は、そこを越えた世田谷区東玉川にある70坪程の借地に3間か4間の平屋を建ててもらい、小さな娘を連れた未亡人の叔母に食事などの世話をしてもらって暮らすようになった。その後、東京商大(現・一橋大)に入学した弟・哲夫も一緒に住むことになる。
K の部屋は南向きの庭に面した洋間で、左側に愛用のアップライト・ピアノが置かれ、右奥にはベッドがしつらえられていた。
私と兄とはこの家にもときどき遊びに行った。 K はいつも私たちを歓迎してくれた。当時は戦争の影響で紙が不足し、五線紙も自由に手に入りにくくなっていた。それでも書き損じた五線紙が何枚かおいてあって、中学生の私たちがそれを数学の計算練習用にもらうのをよろこんでいた。貴重な紙をむだに捨てずにすんでよかったというわけだ。また表紙に
Chopin と書かれた楽譜を見せて、「これでチョピンでなくてショパンと読むんだよ、おかしいだろう?」
と教えてくれたこともあった。リストのラ・カンパネラの楽譜を見せてくれたこともある。おたまじゃくしが縦にいくつもくっついた記号がびっしり並んでいる譜面は、ピアノなど滅多に触ったこともない私にもすごく難しそうに見えた。
「ものすごくむずかしい、だけど本人がこれを弾きこなしたんだから文句は言えないんだ」
といい、夢中になってピアノをたたきだした。そうなるともうかまってはくれない。私たちが引き上げる潮時だった。
昼夜を問わぬピアノの猛練習に近所から苦情が出たのは、この家に移ってからのことである。ある日、私が遊びに行くと、新聞を手に持ちながら、「コマタオトノスケ(駒田音之助?)という名前の投書だ。<困った音>のつもりだろう」と笑っていた。「住所は書いてないが、向かいのおやじにちがいない。ピアノなんぞに現をぬかすとは時節柄怪しからぬことだとほざいておる」。防音処理のない家で、夏などは戸を開け放したままで(冷房なんて無かった)、夜昼と無くガンガンやられては、向かいの人たちも腹が立ったに違いない。だがピアニストはピアノを弾きだすと止まらないものらしい。戦時下に音楽などに明け暮れるとは何事かという風潮があったことへの、ささやかな抵抗でもあったかもしれない。
1943年(昭和18年)になると、日本軍のガダルカナルからの撤退(2月)、アッツ島での玉砕(5月)など、戦況はどんどん不利になっていった。それに呼応するように、9月には大学生・高専生徒に対する徴兵猶予が停止され、学徒出陣がはじまる。この年の11月、
K も召集されて海軍予備生徒になった。一方、中学生も軍需工場などに動員されるようになり、私たちのクラスは3年生後半から三鷹にあった中島飛行機の工場で発動機の部品造りをやらされていた。もとより、
K と会うことなどできなかった。しかしこの頃の私たちは、それぞれ、“天皇の軍隊”にたいして抱いていた信頼と尊敬の念を裏切られるような経験をしていた。
召集された K はまず呉鎮守府管下の大竹海兵團に新兵(二等水兵)として入団したが、そこでの古参水兵による制裁名目の暴行はすさまじいものであったようだ。ある日
K は、その“制裁”によって死亡した一人の予備生徒が、むしろをかけられたまま、ころがされているのを目撃した。彼は面会にきた両親に、かつては憧れてもいた帝国海軍にたいし幻滅を味わったことを語った。その話を聞いた母親は、「ご両親が知りなさったら、どんなにか悲しまれたことだろう」とつぶやいたという。
私の場合は中島飛行機での体験である。当時の私は、焚き火で暖をとったり夜道で時計を見たりするためにマッチを持ち歩いていた。ある日それを憲兵に見咎がめられ、「お前タバコを吸っとるだろう」と頭ごなしにどなりつけられた。殴られはしなかったものの、これは世間知らずの品行方正な少年にとってショックであり、耐え難い屈辱であった。この事件が、絶対的服従の上下関係の上に成り立つ軍隊、あるいはそれに類する組織にたいする私の嫌悪感をはぐくむ最初のきっかけになったことは確かである。
戦局はさらに悪化し、占領されたマリアナ諸島を基地とするB-29 の本土空襲がはじまる。最初の大規模空襲は、1944年11月、私たちが動員されていた中島飛行機の工場だった。その後、工場は林の中に分散し、私たち中学生も昼夜交代で働かされるようになる。年が明けると、10万人が犠牲になった3月10日の東京大空襲を皮切りに、全国の主要都市への焼夷弾と爆弾による無差別爆撃が展開された。高射砲の弾幕も届かぬ高空を悠々と飛ぶB-29
の大編隊の姿は、戦後10年程経った後でも夢に現れたものである。味方の戦闘機の体当たりで墜落したB-29
を1機や2機は見たことがあったが、ほとんどは無傷で飛び去ったように見えた。当時の日記に“当局の発表によれば、約210機来襲、27機撃墜”(5月24日)とか、“250機来襲、47撃墜”(5月25日)などの記録があるが、これらはいわゆる“大本営発表”でしかなかった。5月には、空母からの艦載機P-51による爆撃、機銃掃射もしばしばおこなわれるようになった。低空から直接獲物を狙って撃ってこられるのは、B-29
とは違った格別の怖さがあった。東京はほとんど焼け野原のようになり、田園調布近辺でも爆弾で死んだ人や焼夷弾で焼かれた家があったが、私の家のあたりは奇跡的に無事だった。
そのようなきびしい環境の中で生徒の学習意欲はかえって高まっていた。勉強に飢えていたのだ。私も夜勤明けの帰りの電車の中で、眠い目をこすりながら数学の参考書を読みふけったことを覚えている。高校入試もおこなわれ、倍率が低く、試験も作文だけということも幸いして(戦争のもたらした唯一の恩恵!)私は旧制一高に合格し、一高から動員先への働きかけによって4月末には入学することができた。
そんな日々の中、海軍士官の制服を着た K が突然わが家を訪れたのは、5月22日夜のことである。一高は全寮制だったが、その日はたまたま外出して自宅にいた。兄は北大生になっていて家を離れており、
K と話をしたのは、事実上私だけだった。以下、その日の日記から関連部分をそのまま転載することにする(原文は縦書き、旧仮名遣いのまま)。天皇制軍国主義の教育を受けた16歳の少年の感想である。70年後のいま読み返すと、教育というもののもつ怖さを感じざるを得ない部分もあるが、教え込まれた忠君愛国思想と、あまりにも速く絶たれてしまう才能への愛惜の念との葛藤が表されていると思う。
・・・七時半頃、全く思ひがけなく、恭一君来る。六月一日少尉に任官する予定なりと。これから約一ヶ月山形にて突込みの練習をなすと語る。既に死を一ヶ月後にひかえた人とは思へぬ態度である。特攻隊員と話をしたのは最初だが、全く感動せずには居られない。特攻隊を否定してゐる様な者も、実際話してみれば、きっと感ずるに違いない。
「志願をする迄は苦しい。然し出して仕舞ひ、発表になってしまへば何も苦しい事はない」と語ったが、その苦しくない心は、決してやぶれかぶれな、どうにでもなれといった心では無いと思ふ。僕はかう信じたい。考へに考へ、疑問と否定とを重ねた、妥協のない思考の結果、自分の死によって大君の、同胞の、全人類の為に尽くす事が出来るといふ信念を得たのだと。そして、自ら進んで、自己の心の命ずるがままに、身命をなげうつその行為、これこそ最も美しいものであると思ふ。
それにしても惜しいといへば惜しい人々だ。恭一君も、九州の基地では、暇があればピアノを弾きに、近所の国民学校や女学校に出かけ、又、曲も二十ばかり作られたさうだ。
飛行機の話等を聞く。紫電、天山、極光、秋水等の新鋭機を。願くば恭一君もこれらの最新鋭機にのって見事本懐を果たされんことを。
九時頃、写真をとって後、共に家を出、五反田まで同行す。別れる際、全く感慨無量であった。
このとき秋水がB-29迎撃用の特殊な機体であることなどは聞いた記憶がないし、
K がその後それに乗ることになると分っていたかどうかも、今となっては知る由もない。ともかく私たちは家から現・東急池上線の雪谷大塚駅まで歩き、そこから電車で五反田へ出た。途中ほとんど無言であった。山手線の五反田駅のホームで、私は寮に帰るために渋谷方面行きの外回り電車を待ち、
K は上野方面行きの内回りを待った。手を挙げて電車に乗り込む姿を見送ったのが、
K を見た最後になった。
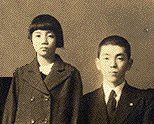
佐藤 明子
兄たちと私は歳が大分はなれておりましたので、私が直接おぼえていることは多くはありません。私の家は、先代から、愛知、岐阜、三重で清酒「大関」の一手販売を手がける問屋でした。毎年11月3日は「酒祭り」といって、トラックに酒樽を積み、幟を立てて走り回ったそうです。私はちょうどその酒祭りの日に生まれました。トラックに乗せてもらっていた兄が帰ってきて、ふすまを少し開け、「どっち?」と聞いたそうです。「女だよ」といわれて「チェ!
」。それが兄と私の出会いでした。
後に母から聞いたところでは、少年の頃、兄たちは岐阜と長野の県境にある恵那山で遭難したことがありました。恭一が中学2年生、哲夫が小学6年生の夏休みで、もうひとり書生として預かっていた遠縁の旧制八高生が同行していました。予定日を過ぎても帰ってこないというので大騒ぎになり、新聞にも連日取り上げられたそうです。たまたま父は灘の蔵元の所へ出かけていて留守。気丈だった母が店員たちを集めて対策本部のようなものをつくり、岐阜県恵那地方出身の店員2人を現地に派遣するなど、大童の対応をしていました。
そして、ついに飛行機を出して空から捜索しようとなったそのとき、山で御神木を伐っていた樵の人に三人が発見され、保護されたという連絡が入ったとのこと。発見されたとき哲夫は編み上げの革靴をはいていましたが、恭一の方はズックの運動靴が破れてはけなくなったのを紐でぶら下げ、血だらけのはだしで歩いていたそうです。そして樵の家では、しばらく何も食べていないことを考えてお粥を作ってくれましたが、疲労困憊した哲夫はそれも食べられないほどでした。ところが恭一はお粥どころか、そばにあった炒り豆をぼりぼりと夢中で平らげてしまったので、その強さとがむしゃらぶりには、みんなが驚いたということでした。
そのような気質と関係があるかもしれませんが、母から聞いたもう1つの話によると、兄はビゼーの「カルメン」のような、人間の血の通った、生々しいオペラこそ本当のオベラだと云っていたそうです。そして将来「道成寺」をテーマにオペラを書きたいとも云っていたということでした。
私が直接おぼえている1つのことは、兄が当時のいわゆる電蓄でクラシックのレコードを聴いているとき、こそっと音を立てようものなら、声には出さなかったものの、ものすごい眼でにらみつけられたことです。だからレコードを聴き始めたときには、抜き足差し足でこっそり部屋を出るようにしていました。
もう1つの思い出は、兄が学徒出陣で出征する直前の昭和18年秋、名古屋や奈良などで開催された東京音楽学校の演奏旅行の機会に、4、5人の同級生仲間と一緒に家に立ち寄ったときのことです。金さん
(※ 註1) といって、朝鮮出身のものすごく背が高い人がおり、コントラバス奏者だということでした。
作曲科の兄はオケではティンパニーを受け持っていましたが、この日は友人の使うシンバルをリュックに背負っていました。そういう気のやさしいところもあったのです。家で食事をし、お酒も入って、みんなは「四季」の中の秋の歌をうたったりして、にぎやかに騒いでいました。
そのとき聞いた話だと思いますが、どこかの演奏会の最中に突然停電があったそうです。ちょうど兄がティンパニーを打っているときでしたが、兄はそのまま拍子をとり続けたので、ほかの人たちも止まることなく演奏を続けられたということでした。指揮者は見えなくても音はきこえるからね、と威張っていました。
(※ 註1)
 戦時中に朝鮮から東京音楽学校に留学した金興教(キム・フンギョウ)。
戦時中に朝鮮から東京音楽学校に留学した金興教(キム・フンギョウ)。
戦後ソウル大学校音楽大学の教師となり、数多くのコントラバス奏者を育てた。1995年没。
NHK交響楽団で永く首席奏者を勤めた檜山薫が出征の際、彼のコントラバスを預かって守り通したという。
海軍に入隊したのち、兄が最初に受取った手紙は私からのものでした。よろこんでくれたことを覚えています。私は学童疎開で遠縁の家に預けられていて、暇だったせいでしょうね。兄からの便りはみな葉書で、それは検閲をしやすくするためだったのでしょうか。私が最後に兄と会ったのは、兄が大竹の海兵団から三重県津の香良洲
(からす) にあった三重航空隊に移った昭和19年の、4月か5月頃でした。正式の面会はできなかったので、外出許可の出た日に、津にあった古くからの取引先の酒屋で会えるよう父が取り計らったそうです。もしもその酒屋に入ったことを見咎められるようなことがあったら、トイレを借りたことにしようというほど慎重にことを運んだと聞きました。検閲の厳しい中で、そのような話をどうやって進めることが出来たのか、今考えると不思議な気もします。
さて当日、父と私がそのお店で待っていると、白い布でくるんだお弁当を手に、海軍の制服姿の兄がやってきました。家からは、お腹を空かせているだろうとおはぎをもって行きました。兄のお弁当は、おにぎりと鰯とにんじんの煮付けでした。好き嫌いが多く、肉が好きで野菜嫌いだった兄が、にんじんを指先でつまんで口に運んでいるのを見て妙に感心したものでした。短剣も見せてくれて何か言ってましたが、私にはよく分かりませんでした。
そのあとで兄から来た葉書には、航空隊全体でおこなわれたマラソン大会で優勝したと書かれていました。兄がそれからまもなく福岡の築城に移動したことは後になって知りました。
この度、岡崎隆様ならびに柴田一哉様のご尽力により、鬼頭恭一の生涯と遺作を世に残すことができるようになりました。そのことを切望しながら11年前に亡くなった哲夫も、生前ならばさぞや喜んだことであろうと存じます。私どもの拙い思い出話を書かせていただいたことと併せ、心より御礼申し上げます。
(2015年 3月1日)
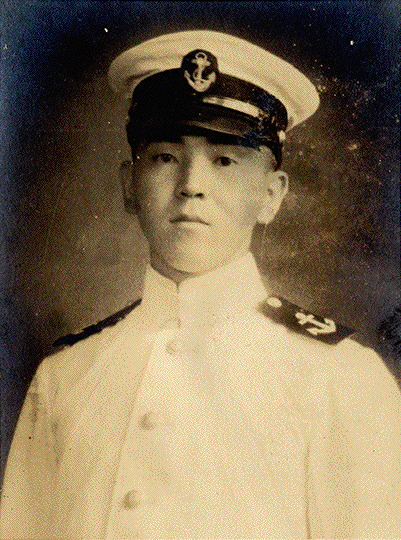
---------------------------------------------------------------------------
佐藤正知(さとう・まさとも) 1928年生、東京文理科大学(旧制)出身、物理学、日本大学名誉教授。
鬼頭恭一は6歳年長の従兄(母が鬼頭家の出で恭一の叔母に当たる)。
妻・明子は恭一の妹。
「鬼頭恭一」のページ
「日本の作曲家」のページ
楽譜作成工房「ひなあられ」のページ
 パストラーレのホームページへもどる
パストラーレのホームページへもどる


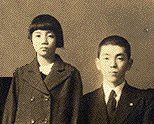
 戦時中に朝鮮から東京音楽学校に留学した金興教(キム・フンギョウ)。
戦時中に朝鮮から東京音楽学校に留学した金興教(キム・フンギョウ)。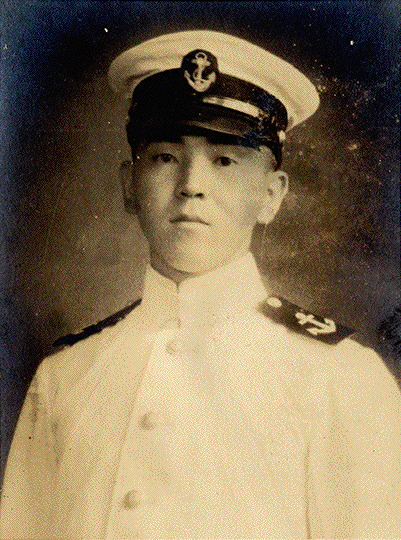
 パストラーレのホームページへもどる
パストラーレのホームページへもどる