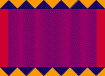 まさよしの千夜一夜物語
まさよしの千夜一夜物語
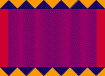 まさよしの千夜一夜物語
まさよしの千夜一夜物語
この物語はフィクションであり、山崎まさよし氏及び実在の人物団体とは関係ありません
|
プロローグ 囚われのミュージシャン
|
|
むかし、あるところに囚われの天才ミュージシャンがいました。来る日も来る日も、やれTVの収録だCMの打合せだ雑誌のインタビューだと自由な時間がありません。3年前、彼が田舎から都会に出てきたときの夢は俺の歌がCDになるといいなという漠然としたものでした。彼の歌は人を惹き付けるものがありました。音楽産業界のドンが見過ごすはずがありません。たちまち、手下を遣わし、契約を取り付けてしまいました。彼の好きな歌は存分に歌えるし、彼の歌はいくらでもCDにしてあげるよというのでした。そのかわり、十年間はその会社のいうとおりに働かなければいけません。彼はなんていい人達だろうと思い、いそいそとサインしてしまったのです。
|
|
第1話 社長の部屋
|
|
レイコは社長のところへやってきました。通された部屋は広々としていてふわふわの絨毯にどっしりとしたマホガニーの机、壁にはなぜかビートルズの大きな写真。反対側の壁にはオ―ディオの機材がいくつかあるのと飾り棚。窓辺にはギターが一つ。他には何もありません。花瓶すら見当たらない殺風景な部屋でした。 |
|
第2話 岸辺
|
|
まさよしはNYの安ホテルにいました。日本を立って、もう一週間経っただろうか。みんな、大騒ぎしているだろうなと思いながら、気持ちの良いのびのびした時間を過ごしていました。目抜き通りを歩いていても誰も振り向きません。小さなレストランで食事をしていても指をさされることもありません。彼はやっと一人に戻れたのでした。 |
|
第3話 ビリーとメグ |
|
メグは捜しまわっていました。ビリーが行方不明なのです。いったいどこに行ったのでしょう。「やっぱりNYなんかに来るんじゃなかったわ。」メグは先月田舎から出てきたばかりの18歳の娘でした。歌が大好きで、いつか認められ、晴れ舞台に出たいと考えてNYに来たのでした。メグには両親が居ません。叔母の家で小さい弟と二人面倒を見てもらっていました。 |
|
第4話 雪ん子 |
|
レイコは今晩も社長の部屋にいました。いくら捜しても、まさよしは行方がわからず、社長は諦めかかっていました。いつのまにか季節は冬になっていました。窓の外はうっすら雪景色で、群青色の闇がほの白く浮き上がっています。
|
|
第5話 ビリーの事故 |
|
まさよしはビリーと暮らすためにちょっとしたアパートを借りました。その家主さんは動物好きだったので、ペットを飼ってもよかったのでした。ビリーはすっかりまさよしになついていました。でも、心の隅にはいつもメグのことが引っかかっていたのです。あんなに優しかったメグ。あんなに仲よしだったメグ。今ごろどうしているんだろう。時々ため息をついているビリーを見て、まさよしは訊いてみました。「おい、ビリー、お前の飼い主はNYにいるんか?」「ブヒッ」「帰りたいんか?」「ブヒ」「でも、どこに居るかわからんしなあ。もう一度ハドソン河に行ってみるか。」一人と一匹はバス停に向かいました。「腹へったなあ。おい、あそこのコーヒーショップで何か食うか。」
|
|
第6話 祭り |
|
Tは飛行機の中にいた。タバコが吸いたい。まさよしは本当にNYにいるのだろうか?社長の命令で、仕事で捜しに行くのだけれど、Tは早くまさよしに会いたかった。まさよしの元気な顔を確かめたかった。Tは窓の外を眺めながら、初めてまさよしと会ったときの事を思い出していた。 しばらくして、盆踊りが始まった。日本舞踊を習っている母親は、さっさと踊りの輪の中に入り楽しんでいる。Tは飲み物を捜して神社の裏に回った。そこには、さっき太鼓を叩いていた若者達が石段に腰をおろして休んでいた。傍の自動販売機でコーヒーとお茶を買いながら聞くともなしに彼らの会話が耳に入ってきた。「今日はむちゃくちゃ緊張したから疲れたなあ」「うん、そやけどオレ明日も緊張するやろな」「そういや、お前明日コンクールやな」「うん、なんかここが痛いよ」胃を押さえて見せたのは真ん中で叩いていた子だ。「心配せんでもええ。お前なら絶対いいとこまでいくやろ、むちゃ歌上手いもん」「確か市民会館2時からだったな。オレ応援に行くよ」「ありがとう。ほんま心強いよ」 Tは自分も行ってみたい気がした。あの子はなんか違う。普通の子にないものを持っている。仕事の虫が動き出したようだ。 「Excuse me」 Tはシュチュワーデスから昼食のトレイを受け取った。まだ、ハワイ上空だった。 |
|
第7話 まさよしとメグ |
|
幸いに、ビリーのけがは大事に至りませんでした。2週間もすると動物病院から退院できました。入院した時よりふっくらしていました。毎晩、まさよしとメグが差し入れを持ってきたからです。ビリーは好き嫌いがないブタでしたが、病院の食事より、二人の持ってきてくれる、スイートポテトだの、ハンバーガーだの、メロンだのが楽しみでした。毎晩のように二人は病院で会いました。二人と1匹はひとりぼっちのときより楽しい時間が持てることに気がつきました。まさよしは、ビリーが退院したらいっしょに暮らさないか、とメグに訊いてみました。メグはいつのまにか、このモシャモシャア頭の片言の英語で冗談ばかり言う日本人の事が好きになっていました。彼の申し出はびっくりしたけど、実はメグには嬉しい言葉でした。「いいわよ」 まさよしはそのアパートで一番広い部屋が空いたので移りました。寝室が二つとリビングと台所と広いバルコニーが付いていました。メグは少ない荷物を持ってやってきました。ドアを開けるとリビングでした。ペパーミントグリーンの壁の明るい部屋でした。家具はテーブルとソファしか見当たりません。窓際にはギターが立て掛けてありました。「さあ、ここが君の部屋だよ。」寝室の一つがメグの部屋でした。こじんまりとしていましたが、ドレッサーやクローゼットが付いていて使いよさそうです。 荷物をしまってリビングに戻ると、まさよしがコーヒーを入れようとしていました。「あら、私がやるわ。慣れているもの。」「うん、ありがとう。」手持ちぶさたなまさよしは窓際にあったギターを手に取りました。そして、手慰みのようにポロポロ弾いていました。メグは驚いてしまいました。なんてなんて上手なんでしょう。自分の事ミュージシャンって言ってたけどこれはかなりの人なんだわ。「ねえ、何か曲を弾いて。」「そうだな・・」♪♪まさよしが弾いたのはメグが聞いたことのないメロディーでした。「それは日本の曲?」「うん、俺が作った。歌もあるよ。」♪♪まさよしはギターを弾きながら歌いました。なんていう声なんでしょう。誰にも似てなくて、強くって、暖かくって、心がぎゅっと抱きしめられるような歌声でした。普段しゃべっている時とは全然違っていました。 「メグも歌うんだろ。」「ええ、一応歌手志望なの。」「じゃ、歌ってみて。」彼が弾いたのはTimeAfterTimeの前奏でした。メグの声は素晴らしく透き通ってどこまでも広がるようでした。彼のギターだと実に気持ち良く歌えました。歌が切々と語りかけるようでした。歌い終わるとなんと窓の外から拍手が聞こえました。道行く人が何人か聞き惚れていたのでした。 しばらくして、メグとまさよしは時々小さなライブハウスに出るようになりました。メグが歌って、まさよしはギターとハーモニカとコーラスでした。まさよしは決して客の前ではソロで歌いませんでした。でも、とても幸せな日々でした。メグはカバーだけでなく、まさよしが作った曲に自分で歌詞をつけて歌いました。素晴らしい歌でした。一度聴いた人は二人のことを強く印象付けられ、そのうち、口コミで二人のことが評判になっていきました。まさよしとメグが作った歌が10曲ぐらいになったある日、一人の男が二人に会いに来ました。 |
|
第8話 M社長 |
|
M社長には二人の子供がいた。上の娘が10歳、下の息子が8歳の時に妻と別れた。 妻は親が決めた許婚者だった。美人で上品な女だった。しかし、Mは結婚前に一緒に暮らしていた女の事が忘れられなかった。女は身寄りがなかった。二人の間には子供までできたのに親のためとはいえ捨てて来てしまったのだった。自分のことを鬼のような男だと思っていた。さぞ、恨んでいる事だろう。どの様に暮らしているのだろう。子供は大きくなったのだろうか。いつもいつも心にひっかかっていた。妻とは心が通わないまま、なんとなく冷たい風が吹いていた。 ある日、下の息子がジャングルジムから落ちて大怪我をした。妻は早く家に戻ってくれと連絡したのに、彼は「君が付き添っていればだいじょうぶさ。今日はどうしても抜けれない仕事があるからだめだ。」と言ったのだ。仕事の虫だった。それ以来、妻との間に深い溝ができ、とうとう、離婚する羽目になったのだった。 彼は昔の女と暮らした山小屋を訪ねて行った。いつか、女の髪に刺してやった山百合がまた咲いていた。しかし、小屋はなかった。わずかに、小屋の周りに積んであった石垣が残っていて、かつての場所を思い出させた。ふもとの村人に女の所在を尋ねても分からなかった。 別れた妻とは会う事はなかったが、二人の子供とはそれぞれの誕生日に毎年一緒に食事をしている。今は二人とも大学生だ。息子の方は、医者の卵、娘は法律を勉強している。娘は、母親に似て美しく賢く育った。息子はMに似て、たくましく背が高かった。母親が懸命に育てたのだ。父親がいなくてもりっぱに素直に育っていた。彼は妻に感謝していた。ここまで育てるにはいろんな苦労があっただろう。しかし、何一つ泣き言を言ってこなかった。見上げたものだ。 Mは仕事に没頭した。人生にやり直しは効かない。誠実であるが故に、自分が人間として情けないという思いをいつも、胸に抱いて、それを忘れたいために、仕事に没頭した。昼も夜もなく働いた。いつしか、ちっぽけな事務所は大きくなり、業界でも名が知られる大手になってきた。会社が大きくなってきても、Mは仕事に没頭した。ライブに行くのも、人と酒を付き合う事も、全て仕事のためだった。ある日、まさよしという天才ミュージシャンを手中にし、金の卵を大事に育て、あらゆる手段を使って作戦を練り、売り出しにかかった。まさよしはMの思惑通りに、あっという間に全国に知らぬものがいないミュージシャンになったのだった。 そんなまさよしが、ある日突然いなくなったのだ。しかも、まさよしの行方を知っていて、毎夜、Mに会いに来るレイコと言う女は、あの山小屋で暮らした女になんとなく似ていた。しかし、そんなはずはない。もう、20年以上も前のことだもの。レイコはどう見ても20代だった。 窓の外を見ると、通りの並木が電飾で飾られていた。もう、クリスマスが近づいていた。 |
|
第9話 Tとまさよし |
|
Tは翌日2時に市民会館に行ってみた。こじんまりとした、古いレンガ造りの建物だった。会場前にはあちこちで出番を待つ若者たちが練習をしていた。どの顔も真剣で、緊張気味だった。建物の中に入ってみると以外に大きなステージがあった。古びた客席に座った。もうコンテストが始まっていた。 ステージはバンドで演奏するもの、ギターデュオのもの、踊りながら歌うものなど様々だった。まさよしは2回出た。1度目はバンドだった。ドラムをやっていた。流行のロックバンドのコピーだった。緊張しながらも楽しそうな様子が伺えた。2度目はコンテストも終わりの方だった。ギターの弾き語りだった。 最初のハープの音で、Tは背筋にビリッと電気が走ったような衝撃を受けた。会場の空気を一瞬で変えたのだ。それまでの、ありきたりな音で倦怠気味の会の流れが止まり、客席のみんなが息を呑んだ。誰も聴いたことのない曲だった。それでいて、昔どこかで聴いたような懐かしい音色だった。それは自由自在にリズムを刻むギターとは別に、もう一人演奏しているようにも聞こえた。そして、あの声は何なんだ。あんな声聴いたことないぞ。何だこの苦しさは。息ができないじゃないか。それまで興味半分で聴いていたTはいきなり張り手を食らった思いだった。歌が迫ってきて聴くものを圧倒するのだ。最後のギターのアルペジオで演奏が終わっても会場は静かだった。一瞬遅れて目が覚めたように静かな拍手があった。感動の拍手だった。ぺこりとお辞儀をして、まさよしは下手に去った。ほっとしたような笑顔には、やはりあどけなさが残っていた。 結局まさよしは、優勝しなかった。審査員特別賞だった。個性的すぎて、流行の音楽とは距離がありすぎて、審査の対象に外れたようだ。Tはしめたと思った。優勝して中央の大会に出て、他の事務所にさらわれる前に彼に出会えた幸運に感謝した。 都会に出てみないか。Tは、バンドの仲間とちょっと落ち込んでいるまさよしに話し掛けた。えっ、俺が?うーん、だって、俺そんなこと考えてみなかった。でも、自分の歌がCDになったら嬉しいな。じゃ、1回だけ行ってみようかな。都会のライブハウスというのも見てみたいから。 契約がどんな内容かもよく読まずにサインをしたまさよしだった。こんなに忙しく時間に縛られるものとは当の本人は夢にも思っていなかった。まさよしの歌は急速に売れ出した。Tはまさよし以上に目が回るような忙しさだった。すべてのスケジュールにタッチしていた。Tは自分の見つけた稀有な才能を世の中に認めさせることに喜びを感じていた。しかし、まさよしが息が詰まりそうなのに気がついていなかった。 TはようやくNYに着いた。まさよしはどこにいるのだろう? |
|
第10話 メグのデビュー |
|
NYはX'masで賑わっていました。ライブハウスのステージを終えて、遅い夕食をとっていた二人のアパートを訪ねてきた男は、レコード会社の人間でした。ライブハウスでのメグの歌を聴いて、スカウトにやってきたのです。「君の歌にはハートがあるよ。君はスターになれるよ。どう、僕に任せてみないか?」メグは有頂天になりました。「これでこそNYに出てきた甲斐があるというものだわ。スターになったら、田舎のおばさんにお礼をしよう。幼い弟にも仕送りができるわ。ね、まさよしも嬉しいでしょう。」男を送り出してからリビングに戻るとそこにはまさよしの姿はありませんでした。テーブルの上に走り書きのメモがありました。 『メグ、おめでとう。これで、君の夢も叶えられるね。しばらくの間だったけど楽しかったよ。サインをする時は、何度も契約書を読むんだよ。僕らの作った曲はみんな君にあげるよ。ビリーを大事にしてください。Merry X'mas そして、 さようなら。 まさよし 』 外はいつのまにか、吹雪になっていました。まさよしの行方はわかりません。 1年後、メグはその男の言ったとおりスターになりました。素晴らしい歌声は世界中に知れ渡りました。彼女がライブのときアンコールで必ず歌う歌はまさよしが作曲してくれたものでした。 ♪♪ いつだったかしら あなたに出会ったのは
|
|
第11話 NYのT
|
|
Tはどこから探して良いか分かりませんでした。まさよしを見かけませんでしたかと訊いても、NYでは誰も知っているはずがありません。ホテルの窓から見る雪景色は日本よりはるかに厳しそうでした。あちこちの路地、酒場、ライブハウスを覗いているうちに、若い女の子がまさよしらしい日本人のギター弾きと歌ってるらしいことを訊きつけました。明日出るからと教えてくれたライブハウスに行ってみると、突然キャンセルになっていました。やっとしっぽをつかんだと思ったのに。諦めきれないTは、教えてもらった住所の書いた紙切れを頼りにまさよしとメグのいたアパートを探し当てました。そこには、引越しの荷造りをしているメグがいました。 「まさよしはどこ?」「あなたは誰?まさよしはいないわ。突然いなくなったの。何かに追われているようだったから、私がデビューすることになったから、姿を隠したんだわ。そうなのね、あなたから逃げていたのね。まさよしが何をしたっていうの?」 Tはショックでした。返す言葉がありませんでした。まさよしによかれと思っていたことが、逃げ出さずにはいられない状況だったとは。街はクリスマスが終わり新年を迎えようとしていました。新年のカウントダウンが始まりました。陽気なイタリア娘が、ぼうっと立ち尽くしていたTに抱き着いてほっぺたにキスをしました。どうやら、新年になったようです。おめでとうとつぶやいて、Tはまさよしの歌を思い出しました。 そうだ、まさよしは何にも縛られるのがいやなんだ。縛られるぐらいなら、名前のない鳥でいいんだ。今ごろは自由に空をさ迷っているのだろう。さびしいだろうに。願わくば元気でいて欲しいものだ。きっと、今ごろは誰も知らないどこか小さな街で、ギターを鳴らして好きな歌を歌っているんだろうな。Tはホテルを引き払って日本に帰ってきました。社長には、まさよしの影も形も見つからなかったと報告しておきました。 その年のNYの冬は記録的な大雪でした。 |