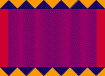 まさよしの千夜一夜物語
まさよしの千夜一夜物語
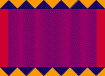 まさよしの千夜一夜物語
まさよしの千夜一夜物語
この物語はフィクションであり、山崎まさよし氏及び実在の人物団体とは関係ありません
|
第19話 レインソング |
| 雨は止まない。まさよしは波止場の倉庫の軒先に雨宿りしていた。どこかで、見た海だった。雨の向こうに山が見える。右の方には大きいクレーン左には灯台。ああ紛れもなく、そこは彼の故郷の海だった。ここを離れたのは何年前だろう。 あの日、まさよしは彼女にきちんとサヨナラを言いたかった。僕は都会に出るよ。夢がかないそうなんだ。今まで言えなかったけど、君の事とても好きだったよ。だけど、君について来てくれとは言わない。まだ、どうなるか分からないもの。生活のメドがついたら君を迎えに行くよ。それまで、待っていてくれるかい。だが、まさよしは言えなかった。あの日も今日のような雨が降っていた。 一月ほど前から二人はけんかをしていた。彼女は仕事を持っていた。その付き合いで約束の時間に遅れたのだった。まさよしはせっかく彼女に内緒でとったコンサートのチケットをパーにしてしまった。彼女がお気に入りの海外のアーチストが来るから、その晩二人で行こうと思っていたのだ。彼女は電話で謝ろうとした。だけど、彼女の仕事を理解してくれず、子どものようにいつまでも腹を立てているまさよしに業を煮やしてしまった。その後、二人とも意地を張って連絡しないまま時間が過ぎて行った。ほんとはあの晩、まさよしはプロダクションと正式に契約した事を彼女に話したかったのだ。その大事な事を伝えたいのにずるずると約束の日が近づいてきた。とうとう、明日立つというあの日、荷造りをしていた彼の部屋のドアを小さくたたく音。彼女だった。 やあ、久し振り、どうぞ。彼女はほっとした様子だった。訪ねようかどうしようか散々迷っていたのだった。今日は雨だから、彼も休みのはずだと思って思いきってやってきたのだ。二部屋の安アパート。傘のしずくを切りきちんとたたんで傘立てに入れ、部屋に上がった。まさよしのタバコの匂いがする。来て良かった。いつものようにコーヒーを出してくれたまさよしに「この前はごめんね。元気にしてた?」「うん。」「私ね、ちゃんと気持ちを伝えようと思って、ずっと考えてたの。」彼女は、彼の事をなおざりに考えていないこと。だからこそ、一人の人間として自立したいから、今は仕事を大事にしたいこと。まさよしも自分の夢に向かってがんばって欲しいことなど言いたい事がいっぱいあった。それをどうやって話そうかと何気なく部屋の片隅に目をやる。ダンボールがいくつか積まれている。普段から家具の少ない部屋だったが、いつもにましてがらんとしている。 彼女の目がみるみる潤んだ。全てを察したのだ。あるオーディションでプロダクションの人に声をかけられたということを前にまさよしに聞いていたからだ。「話が決まったの?」「うん」「いつ行くの?」「明日」「そう、よかったね。がんばってね。さようなら。」ショルダーバッグの肩紐を引っつかみ後ろを振り返らず彼女は部屋を出た。ドアを後ろ手にバタンと閉め、階段を駆け下りた。大粒の涙が頬を伝う。まさよしは何も言えず、彼女を引きとめもせず、車の音が遠くなって行くのを聞いていた。玄関には彼女の白い傘が置き忘れてあった。 雨が小振りになった。僕は何故ここに居るのだろう。いまさら何処に行けばよいのだろう。 |
|
第20話 僕はここにいる |
| ユキは傘を忘れてきたことに気がついた。あてどもなく運転し、気がついたら、まさよしとよく歩いた海辺。雨のフロントガラスの向こうを遠く大型の輸送船がゆっくりと進んでいく。にじんで見えるのは雨のせいばかりではない。ぬぐってもぬぐっても、涙があふれてくる。今になって、彼がユキの中に占める存在の大きさに気がついた。 ユキは彼に初めて会った日のことを思い出した。ユキがまだ美大生だった頃だ。兄の入院していた病院の近くの公園だった。ユキの兄は両親の期待を一身に集めていた医者の卵だった。幼い頃から成績優秀で普段は言葉数は少なく静かだったが、正義感が強く、弱いものいじめをしている者には容赦が無かった。ユキは平凡な女の子だった。両親は何につけ兄と比べるので、兄に対していつも引け目を感じていたが、一方では誇らしくも思っていた。兄は卒業するとすぐアフリカに渡った。少しでも早く医者を必要としている人々のために働きたかったのだ。そして、慣れない土地で昼夜無く働き詰めに働いたあげく体を壊してしまい日本の病院に移されたのだ。兄はユキに対しては、いつも優しかった。お前はお前のままでいいんだよ。お前は一人で自分の心を磨けばいいのさ。その心を欲しいという人がくるまで、じっと待っていれば良いんだよ。いつか兄の言ってくれた言葉が今でも心に残っている。 病院のバス停は嫌いだ。人生に疲れたような人しかいない。次のバス停まで公園の中を歩いて行こう。そこは有名な薔薇園のある公園だった。何百種という薔薇が咲き乱れていた。ベンチに腰を下ろして見るともなしに薔薇の畝を見ていると仔犬が走ってきた。紐を引きずっている。どうしたんだろうと思っていると、向こうからボサボサ頭の若者が走ってくる。すいません、その犬捕まえてくださあい。ユキは家で昔犬を飼っていたことがあるので、すぐに、足で犬の紐を踏みつけ、逃げないように、持ち手をしっかり握った。「ありがとうございます。助かりました。」笑顔が少年のようにまぶしい。いくつぐらいだろう、まだ、十代かもしれない。「あなたの犬なの?」「いや、違うんです。バイトなんです。僕がちょっと目を離しているる隙に逃げだしちゃって。」「あら、ちゃんとしなくちゃ、クビになるわよ。がんばってね。」「うん。あ、お礼にコレあげるよ。」若者はさっき買ったみたらしを彼女に差し出した。「さては、これを買ってる間に逃げられたんだね。」「へへ、当たり!」「じゃ、遠慮無くいただくわよ。」二人はベンチに腰をかけ、みたらしを食べながら、前からの知り合いのようにくったくなく笑った。ユキがこんなに笑ったのは久しぶりだった。 ユキが公園を歩いて帰ろうと思ったのは、また、あの若者に出会えるかも知れないという思いが心の隅にあったのだろう。この前と同じベンチに腰掛けて今日は来ないのかなと時計を見ようとすると、「誰か待ってるの?」と後ろから声。ユキは雷でも落ちたようにびっくりした。思わず、真っ赤になる。あの若者だ。「俺ずっと見てたんだよ。」「わ、ヒマジン。」彼は毎日のようにここで彼女を待っていたのだった。「ね、この前訊くの忘れてたけど君の名前なんて言うの?俺まさよし。」いつのまにか「俺」「君」になっている。「私はユキ。大学生。今年で卒業なの。」「ふーん、じゃ俺より3っつも年上なんだ。同じぐらいかと思った。」ユキはちょっと複雑な気分。この若者はやっぱり十代なんだわ。だのにこのタバコの吸い方の板についていること。きっと不良なんだ。「今日はみたらしじゃなくて俺の知ってる店に行かない?」今日は犬を連れていない。その肩にあるのはギターケースだった。 |
|
第21話 YOUR SONG
|
| まさよしがユキを連れて行ったのは小さな店だった。レンガの壁に分厚い一枚板のドア。まさよしは片手でドアを開け顔だけ入れて覗いてから、後ろを振り返り、おずおずとした様子のユキを手招きした。ユキは逃げ出すのなら今だ、と思った。まだ、2回しか会っていないどこの誰とも分からないこの若者。私は何でこんな所にのこのこと付いて来たのだろう。だけど、ユキは逃げ出さなかった。あまりにも、まさよしの笑顔が屈託なかったから。その笑顔を信じようとユキは思った。中は落ち着いたイギリス風の居酒屋だった。まさよしは当たり前のようにカウンターの隅に腰掛けユキはその隣に座った。「あれ、今日はとびきりのかわいこちゃんを連れてどうしたんだい?」「や、マスター、ごめん、遅くなって。この人に何か作ってあげて。何がいい?」「コーク・ハイ」ユキはそれしか知らなかった。「じゃ、俺はいつものコロナビール」何なんだろう、こいつはオッサンか?「ねえ、ここはよく来るの?」「俺ここで弾き語りのバイトやってんだ。君に聴かせたいなと思って」意外だった。彼が歌を歌うなんて?そんな繊細な人には見えない。さて、ビールを一気に飲んでしまうと、まさよしは奥のステージに向かった。ステージといってもドラムセットとマイクとアンプがおいてあるちょっとした空間だった。 「こんばんは。今日は何から行こうかな?なんかリクエストあります?」客はビートルズだのクラプトンだのビリー・ジョエルだのいろいろ言う。そして、彼が選んだのはエルトン・ジョンのYOUR SONG。その、出だしのギターにユキは心がキュッとなった。何だろうこのギターはなんて寂しくて暖かいんだろう。そして、彼の歌。その声はユキが今まで聴いたことのない、暖かく強く優しく寂しい声だった。それはユキに語り掛けているように思えた。彼の声が直接心に響いた。彼はその後も10曲近く1時間ほど歌っていた。どんな曲も彼の歌だった。まるで、彼が作った歌のようだった。そして、彼の楽しそうなこと。彼は働いているのではなく、楽しんでこの仕事をしているのは明らかだった。 「楽しかったわ、ありがとう。最終バスに乗り遅れるから帰るね」「うん、来てくれてありがとう。また、会える?」「ええ、土曜日のあの時間にはいつもあのベンチに行けると思うわ。」「じゃ、また待ってるよ。」「あ、あなた知ってる?」「何?」「あなた、すごく歌が上手よ」まさよしは何も言わずにっこりした。うん、俺は歌で気持ちを表す方が簡単なんだよ。最初の曲は君に歌ったんだよ。と言いたかったけど言葉が出てこない。「じゃ、気をつけて。俺はもう少し仕事があるから」 ユキはバスに揺られながら彼のことを思っていた。不思議な人だ。年下なのに人生が何なのか知り尽くしているような瞳、自分が何物なのか知らないで地上に降りてきた天使のような笑顔、歌うようなメロディーとうねるようなリズムを作り出すしなやかな手、聴いている者の心をすっぽりと包んでしまうあの誰にも似てない声。 |
|
第22話 あじさい |
| まさよしはぼんやりと歩いた。いつか居た街なのだろうか。夢の中を歩いているのだろうか。いつのまにか、懐かしい場所に居た。そこは彼女とよく来た公園だった。あじさいの季節だった。 あの時もあじさいがきれいだった。お兄さんが亡くなった時、あの白い傘をさしていつものベンチのそばに立っていた彼女。ほっそりとした後姿がいつもより一段と小さく、今にも消えそうに見えた。彼女は今まで優しいもの、美しいもの、正しいものにしか知らなかったので、現実の理不尽な残酷さに耐えられなかった。彼女の誇りだった最愛のお兄さんが亡くなって、今は泣くこともできなかった。 まさよしは一目でわかった。幾度か会っているうち、彼女の家庭、彼女の過ごしてきた時間、彼女の夢、彼女が愛しているものを知っていた。だから、その後ろ姿だけで彼女の悲しみがどんなに深いものか、どんなに打ちひしがれているかがわかった。しかし、まさよしは彼女に何も言えなかった。何も言わずに公園の周りのあじさいの続く道をバス停まで送っていった。バスを待つ間もずっと黙っていた。やがて、彼女の乗るバスが来て小さくさようならと振り向いた彼女の目にやっと一滴の涙が見えた。ああ俺はなんというでくのぼうなんだ。何で彼女を思いきり泣かせてやれなかったんだろう。 あれから、一週間が過ぎた。彼女はもう、あの公園には姿を見せない。もう病院には用は無くなったのだから当然かもしれない。まさよしは彼女の住所も電話番号も聞いてなかったことに気がついた。ユキと言う名前しか知らなかった。確か彼女の家は産婦人科の医院だと言っていた。電話帳で調べるとその街には5軒だけしかなかった。上から順番にかけていって、3軒めで当たりだった。「ユキさんいらっしゃいますか」はいユキはおりますが、どちらさまですか。「ぼく、まさよしと言います。そう言えば分かると思います」ちょっと、お待ち下さい。と、たぶん、お母さんだろう。 「はい、ユキです」この前は何もしてあげられなくてごめんね。俺、ずっと君のこと考えていたんだ。と言うつもりだったが、やはり言葉は出てこない。いきなり、ギターを持ってきて歌い出した。「あじさい」という歌だった。 ユキは小さく笑った。「ありがとう。まさよし」まさよしは自分の歌がユキに伝わったのが単純に嬉しかった。ユキが受話器を置いて部屋に戻り、兄が亡くなって初めて、ありったけの涙を流せたのを彼は知らない。 |
|
第23話 夏のモノローグ |
| 夕方になった。まさよしはまた、海辺の道に出た。そこは、彼女と遊んだ浜辺に続く。カモメが数羽波間を飛んでいた。あれから、いくつか季節が過ぎていった。 夏 彼女は前より少し強くなった。初めて、アルバイトをした。浜辺で氷を売っていた。夕方になるとまさよしも仕事から帰ってきた。二人で夕日の中を帰るのが楽しかった。彼女はまさよしにだけは思いきり甘える。「マー、私ボートに乗ってみたい」「マー、私ここで泳いでみたい」「マー、助けて、私泳げないの」「マー、私ラムネ飲みたい」「マー、私帰りたくない」「マー、私のこと好き?」 秋 彼女は生き生きとしている。彼女はまさよしがそばにいれば何も怖くない。二人一緒に運転免許を取る。ドライブに出かける。まさよしが苦労して買った中古の軽自動車。山道でエンスト。やっと通りかかった車に助けてもらい、彼女の家に送って行ったのは真夜中。まさよしは彼女のお父さんに殴られる。お母さんが近くにあった布で鼻血を拭いてくれた。しかし、それは雑巾だった。 冬 彼女は美しい。まさよしは時々口をつぐみ、彼女をじっと眺める。彼女は、まさよしに誕生日のプレゼントをする。手編みのセーター。オフホワイトの極太でざっくり編んであるが、軽くて暖かい。網目が大きい市松模様になっていて彼のふわふわの髪を引き立てる。彼の持っているセーターはこれだけだ。彼はあるプロダクションの新人募集オーディションを受ける。ボロボロのジーパンに彼女の編んだセーターを着て行く。彼女がそばに居てくれるようだった。 春 彼女は考える。自分のこと、まさよしのこと。彼女は大学を卒業して、設計事務所に就職した。彼女はガウディのような建築家になりたいという自分の夢に一歩踏み出した。通勤にお父さんのお古のスポーツカーを貰う。彼女はキャリアを積みたい。仕事が忙しくてなかなかまさよしに会えない。彼女は彼の知らない世界にいる。彼女は、もうまさよしに甘えない。 夕暮れが濃くなる。家路に急ぐ人とすれ違う。街の灯りがだんだん点っていく。まさよしはぼんやり波間を見つめていた。あの夏の日、なぜ、彼女に答えなかったのだろう。うん、君が大好きだよと。ずっと、俺のそばに居てくれるかいと。今だったら、言えるだろうか? 水門近くの橋を渡ると、そこは懐かしい海辺だった。と、そこに、昔の彼女のと同じ型の車が止まっていた。古い外国製のスポーツカーだった。 |
|
第24話 振り向かない |
| 俺が彼女との間に噛み合わないものを感じたのはいつ頃からだったろうか。それまでは何でも話してくれたのに、俺の馬鹿話に涙が出るほど笑っていたのに、いつからか俺の知らない彼女がいた。彼女はどんどん、大人になっているのに俺だけが置いてけぼりを食ってる感じがして、不安なのに、その思いを素直に口にできずに、自分から距離を置いていた。彼女はちゃんと仕事に就いた。夢に向かって一歩踏み出した。俺は、都会に行く。来いよといってくれる人がいるから。ずっと迷っていたんだ。彼女に相談したかったのにできなかった。自分の才能は信じている。だけど、先のことは分からない。彼女について来いなんて言えないよ。明日のことも分からない、根無し草なのに、彼女まで巻き添えにできないよ。 ドアは僅かに開いたまま、彼女の白い傘もそのまま。彼女が取りに戻ることはないだろう。
ユキ、君のこと、考えると、胸が疼く。
まさよしは、長い時間かかって手紙を書いた。 だが、彼女に渡すすべもなく、くしゃくしゃにまるめてポケットに入れる。 |
|
第25話 星に願いを |
| 彼女はいつの間にか眠っていた。気がつくと雨は止んでた。もう、辺りは夕闇が迫っている。遠くに灯台の光が見える。車のドアを開け外に出る。海はもう波目が見えない。目を凝らすと、雲の隙間から星が見える。 きっと、マーはあの星のようになりたいんだわ。いつまでも、こんな小さな町に燻っていてはいけない。マーは私なんか必要じゃない。十分一人で生きていける。私だって一人で生きよう。私も私の星を見つけよう。さよならマー。夢を叶えてね。今までありがとう。 まさよしはびっくりした。車から降りて海を眺めているのは、まさしく、あの日のユキだった。声をかけようと思ったのに声が出ない。そう、声をかけてはいけないのだ。彼女はこの後、幸せな結婚をしたのだった。彼女のお兄さんの友達だった。彼女のことを小さい頃から知っていて兄のように大きな愛情で包むことができる男だった。家庭を持った後も彼女は設計の仕事をしていた。まさよしはユキの結婚とその後の様子を友達の手紙で知っていた。今声をかけるとすべてが変わるかもしれない。ユキは俺についてきてくれるだろうか?行かないでくれと泣きすがるだろうか? いや、俺はそんなことを望んでいるわけではない。ただあの日彼女にきちんとさよならが言えなかったことが、心にいつまでもひっかかっているのだ。 まさよしは、決心したように彼女の方に歩き出した。ユキは足音に振り返り、近づいてきた男がまさよしだとわかると、びっくりしたようにこっちを見ている。声が出ない。何か書くものがないかとポケットをまさぐると、なぜか、あの日の手紙がくしゃくしゃのまま入っていた。まさよしは、だまってその手紙を彼女に渡した。手紙を読んだ彼女は泣き崩れることもなく、晴れやかな笑顔だった。しかし、まさよしは、悲しかった。体中の血液が逆流しているようだった。このまま彼女をかっさらっていきたかった。これで、ほんとうのさよならだね。もう二度と会うことはないだろう。 背中をかがめ、覗きこむようにユキの顔を両手で包み、かわいいおでこにそっとキスをして、彼女の細い肩をぎゅっと抱きしめた。髪と髪が絡まった。ずっとこうしていたかった。ようやく、彼女の耳元で、低く囁くように「さよなら」と言うと彼の姿は夕闇の中にかき消えてしまった。そして、たちまちのうちに星空は見えなくなり、雷鳴が轟いた。 |